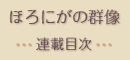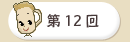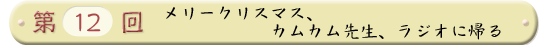● 濱田研吾 ●

*1 CIEラジオ課時代の五味正夫(『五味正夫君のこと』私家版/昭和34年6月)

*2 NHKラジオ『英語会話』収録中の平川唯一(平川洌『カムカムエヴリバディ・平川唯一と「カムカム英語」の時代』NHK出版/平成7年5月)

*4 『カムカム英語』新聞広告(『昭和広告60年史』講談社/昭和62年7月)
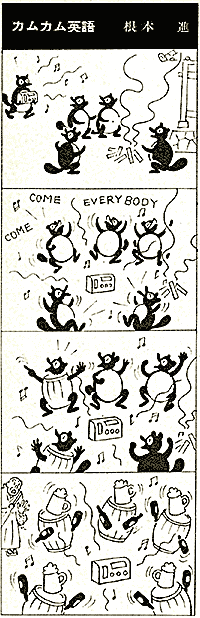
*6 根本進「カムカム英語」(『ほろにが通信』第18号)
昭和26年は、『ほろにが通信』をはじめ、紙媒体で宣伝活動を進める朝日麦酒にとって、節目の年となった。同年9月の中部日本放送を皮切りに始まる、民間放送局の開局である。 NHKがテレビの本放送を開始したのは、昭和28年2月。同年8月には、民放初の日本テレビが開局し、広告業界に大きな変化をもたらす。 とはいえ、当時のテレビ契約台数は1万台に満たず、企業にとっては、CMやスポンサー番組の制作が迫られる民放ラジオのほうが重大事となった。
民放時代の波に乗る必要があるのは、朝日麦酒も当然である。しかし、創業してわずか2年の同社には、映画、舞台、音楽を用いたタイアップ事業の経験がない。 昭和25年に、ビヤガーデンとプロ野球をセットにした「ハッピービヤナイター」(後楽園球場)に協賛したぐらいである。
こうした状況のなか、宣伝をつかさどる業務第1課が困惑したのは無理もない。ブレーンの飯沢匡に全権をゆだねるわけにはいかず、自分たちの手で民放時代を受け止めなければならない。 同課の嘱託社員だった三國一朗は、《コマーシャル・メッセージというものを起草する仕事が増え、その案文の社内的処理、ラジオ東京への送達業務、放送局側の考査部門、営業部門との折衝、 担当アナウンサーとの打ち合わせ、モニター業務、そのほか未経験の仕事が山積》(『話術』筑摩書房/昭和59年6月)と当時の慌しさを回想する。 いっぽうで広告代理店は、企業の困惑のそばで活発な動きを見せ、急成長を遂げていく。吉田秀雄が率いる「電通」は、その最たる存在といえよう。 ただし、朝日麦酒と電通は蜜月関係になく、関係を深めたのは「中央放送広告」の社長・五味正夫(*1)とであった。
業務第1課が本格的にラジオ対策をはじめたのは、昭和26年夏。その年の12月に迫っていたラジオ東京(現・TBS)の開局にあわせ、準備を進めていた。 そんなとき、銀座7丁目の朝日麦酒本社に、CIE(民間情報教育部)ラジオ課の出身で、広告代理業を始めつつあった五味(当時38歳)が訪ねてくる。 初対面の五味の印象について、業務第1課長の長谷川遠四郎は、《快活な、そしてきらきら光る注意深い眼、歯切れのよい言葉、要を得て急所をはずさぬうけ応え。 (略)スマートなのは決して彼の外見ばかりでない》(『五味正夫君のこと』私家版/昭和34年6月)と振りかえる。
この初会見の席で、長谷川と五味は意気投合する。民放のノウハウのない長谷川にとって、五味は心強い味方であり、ここに両者の思惑が一致した。 それはそのまま朝日麦酒と中央放送広告(創立は26年12月)との結びつきになり、朝日麦酒の広告代理業を引き受けた同社は、数多くのスポンサー番組やタイアップ事業に関わっていく。 そんな記念すべき初会見の席で五味は、NHKラジオ『英語会話』の講師だった平川唯一(*2)の復活プランを提案するのである。
*
平川唯一。戦後のラジオに親しんだ世代には、忘れえぬ懐かしい名前のはずである。平川は、アメリカでの役者修業をへて、昭和12年からNHK国際部に在籍した。 そのまま終戦をむかえ、昭和21年2月から『英語会話』の講師をつとめることになる。アメリカ側の指導を受けてスタートした同番組は、幸いにも大ヒット。 童謡「証城寺の狸囃子」をアレンジしたテーマソング「カムカムエヴリバディ」が流行し、終戦直後の人気ラジオ講座として欠かせぬ存在となった。
番組のヒットにあわせ、平川の知名度は上がった。巷では「カムカム先生」「カムカムおじさん」と呼び親しまれ、ラジオスターとして一世を風靡する。 昭和22年1月には有楽座の舞台「カムカム・ロッパ」に特別出演し、張り切りすぎた平川の芝居に対して、座長の古川緑波が困惑する1幕があった。
しかし昭和26年2月、平川は『英語会話』の講師を降板してしまう。突然の降板劇だったため、平川のギャラ問題など多くの憶測がとんだ。 平川の次男・洌が著した『カムカムエヴリバディ・平川唯一と「カムカム英語」の時代』NHK出版/平成7年5月)には、番組を自負する平川とリニューアルを考えるNHKとのすれ違いが、 降板の一要因になったと書かれている(『英語会話』はそのまま講師を代え、現在の『ラジオ英会話』へとつづく)。
そんな平川の講師降板を、親交のあった五味は惜しみ、民放で復帰させるべく動き出す。五味の提案を受けたラジオ東京は、その話を受けたが、条件としてスポンサーの獲得を出した。 その意を受けた五味はスポンサー探しに奔走し、たどり着いた朝日麦酒で業務第1課長の長谷川と出会う。そこで意気投合した長谷川に、平川の復活プランを提案したのは、ごく自然な成り行きといえる。
こうした動きがあることを、五味は、平川に隠していた。そして、放送が本決まりになったうえでテニスに誘い、「もし先生が私に勝ったら、素晴らしいビック・ニュースをお伝えする」と告げた。 その勝負に勝った平川は、ここで初めてラジオ東京版『英語会話』の話を知る。五味は、最初から負けるつもりでテニスに誘い出し、平川を喜ばせようとしたのかもしれない。
むかえた、昭和26年12月25日・朝7時15分(*3)。『英語会話』は『カムカム英語』と名をあらため、ラジオ東京の記念すべき開局の朝にスタートを切った。 第1回放送では、《この時間を提供してくださるアサヒビールの、実に気持ちのよい、温かいご好意があったればこそ》(『カムカムエヴリバディ』)と語り、平川みずからスポンサーへの謝辞を口にしている。
朝日麦酒としても、『カムカム英語』は、内容、知名度、いずれもイメージは悪くない。新聞広告(*4)を出し、『ほろにが通信』に紹介記事(*5)や4コマ漫画(*6)を載せるなど、積極的にPR。 当時売れっ子の三木鶏郎にテーマソングの制作を依頼し、三木が作詩・作曲を手がけた『僕は英語の習いたて』(*7)を放送中に流したりしている。 肝心のコマーシャルづくりにも熱心で、三國一朗は毎回異なるCMコピーを考え、陳腐にならないように気くばりを見せている。
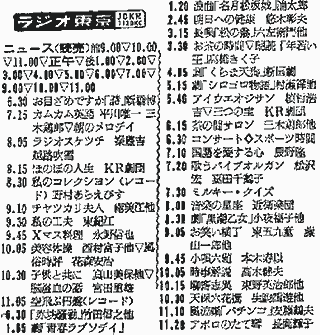
*3 昭和26年12月25日付「読売新聞」
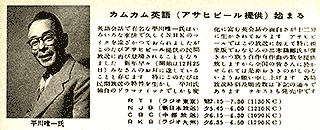
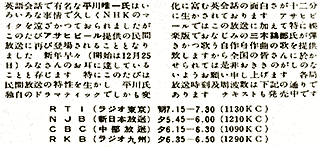
*5 「カムカム英語始まる」(『ほろにが通信』第17号)

*7 三木鶏郎作詩・作曲「僕は英語の習いたて」楽譜(『アサヒビール宣伝外史 揺籃期の栄光と挫折』中央アド新社/平成11年3月)
これだけを見ると、番組は末永く続くように思える。しかし、実際はNHK時代ほどの人気は得られず、復刊したテキスト(*8)の売り上げも芳しくない。 番組は当初、ラジオ東京、中部日本放送、新日本放送(現・毎日放送)、ラジオ九州の4局ネットで、NHKにくらべて浸透度に限界があった。 結局、ラジオ東京と朝日麦酒は1年で番組を打ち切り、そののち文化放送にキー局を移して続行するが、聴取率が回復しないまま昭和30年7月に放送終了。 一世を風靡したラジオ番組としては、さびしい終幕をむかえてしまう。

*8 民放時代に刊行されたラジオテキスト『カムカム英語』(日東出版社/昭和29年10月号)
放送当初の意気込みを考えると、朝日麦酒のスポンサー契約打ち切りは早かったが、1年という区切りの良さは妥当ともいえる。民放初体験の企業からすれば、契約を更新するか否か悩んだのかもしれない。 それに当の平川は、最初にスポンサー契約に応じた朝日麦酒の決断に感謝し、それ以上に番組復活に奔走した五味の心意気を忘れなかった。 そのことは、早世した五味への追悼文「陰の捨石よ、永遠なれ」(『五味正夫君のこと』)を読むとよくわかる。
朝日麦酒がスポンサーとしてのビジネスを優先させたのは当然だが、少なくとも五味は、“ビジネス”より“情”が勝っていたように思える。 五味と平川の友情が、朝日麦酒の放送参入のきっかけをつくり、五味をアドマンとして独り立ちさせるきっかけになったと書くべきか。 『カムカム英語』は長続きしなかったが、朝日麦酒はこれを機に、電波媒体を用いた宣伝活動を本格化させていくのである。
(つづく)
- プロフィール
- 濱田研吾(はまだ・けんご)
- ライター。昭和49年、大阪府交野市生まれ。
- 日本の放送史・俳優史・広告文化史をおもに探求。
- 著書に
- 『徳川夢声と出会った』(晶文社)、
- 『脇役本・ふるほんに読むバイプレーヤーたち(書籍詳細へ)』(右文書院)。
- 『三國一朗の世界・あるマルチ放送タレントの昭和史』(清流出版)。
- 注記
- 本稿の無断転載は、ご遠慮ください。
- 図版は、特記なきものは筆者所蔵のものです。