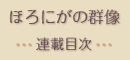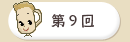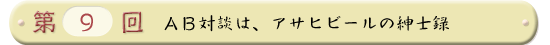● 濱田研吾 ●
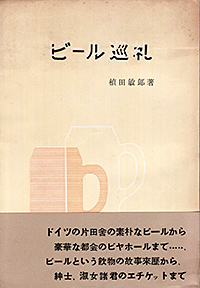
*1 植田敏郎著『ビール巡礼』(白水社/昭和29年7月)

*2 植田敏郎著『ほろにが随筆』(河出新書/昭和31年7月)

*3 『甘味(お菓子随筆)』(双雅房/昭和16年2月)

*4 『あまから随筆』(河出新書/昭和31年2月)
コピーライターの河田卓は、『ほろにが通信』についてこう書く。《当時を知るある人の話によれば、巷間の評価は圧倒的に高く、それに書いたかどうかで、執筆者の評価が決まったほどだったという》 (『キャッチフレーズ三〇〇〇選』誠文堂新光社/昭和51年3月)。たしかにどんな雑誌でも、そこに登場する顔ぶれの個性や多彩さで、誌面のイメージは決まってしまう。
『ほろにが通信』のばあい、10ページ前後の企業PR誌としては豪華な執筆者(ゲスト)がそろい、しかも、ただ有名人をならべただけではなく、人選そのものにセンスが感じられた。 品を損なわない、華やかな顔ぶれのビールの雑誌。『ほろにが通信』を語るうえで、このキーワードは外せない。
ビールの雑誌らしい記事といえば、まず、エッセイや小説があげられる。テーマはビールか酒場めぐりに決まっていたが、飯沢匡の人脈をいかした執筆者の面々は、一流誌にひけをとらない。 大日本麦酒から分割独立したとはいえ、創業まもない朝日麦酒だけの力では、これだけの顔はならばないだろう。
それぞれの文章を紹介する余裕はないが、書き手とタイトルをながめるだけで、この雑誌が持つ世界観は伝わってくる。 山田耕筰「愉しいビールの味」(1)、永井龍男「銀座酒場めぐり随伴記」(2、3)、西脇順三郎「英國民の生活とビール」(4)、徳川夢声「想麦酒恋」(4)、 秋田實「ビールとユーモア」(5)、奥野信太郎「渋谷のみ歩る記」(7)、村上元三「わたしのビール」(12)、近藤東「京都のみ歩き」(12)、玉川一郎「ビールのペーソス」(18)、 野口久光「ビールの杯から生れる幻想のバレー映画」(18)、城昌幸「ビールミステリー・夏の日の恋」(22)、伊藤晴雨「ビールが人を殺した話」(24)、水谷準「ビールコント・河童のチャルメラ」(25)、 安藤鶴夫「吾妻橋歳月」(27)、東郷青児「パナッシェの味」(35)、岡本太郎「偉大なるいやったらしさ」(36)、梅崎春生「ほろにが東京散歩」(37)、米川正夫「欧州麦酒遍歴」(42)、 式場隆三郎「夏のない湖水の国」(47)、植田敏郎の連載エッセイ(41~55)など、ラインナップはなかなかシブい(カッコ内は掲載号)。
惜しむらくは、ここにあげた文章のほとんどが、単行本になっていないことだ。文章がまとめられたのは、植田敏郎の2冊の著書『ビール巡礼』(白水社/昭和29年7月/*1)と 『ほろにが随筆』(河出新書/昭和31年7月/*2)しかない。これでは、少しさびしい。永井、奥野、梅崎の酒場エッセイなど、編集の仕方によっては魅力あるアンソロジーが編めるのではないか。
PR誌のアンソロジー本としては、明治製菓の『スヰート』掲載の文章が、『甘味(お菓子随筆)』(双雅房/昭和16年2月/*3)として1冊にまとまっている。 それをまねて『苦味(ビール随筆)』として編んだら、おもしろいと思うのだが……。
『あまカラ』(甘辛社)のアンソロジー『あまから随筆』(河出新書/昭和31年2月/*4)や、全3巻の『アンソロジー洋酒天国』(TBSブリタニカ/昭和59年)のようにするのも一案か。
*
『ほろにが通信』のイメージを高め、雑誌への信用度をより深めたものとしては、「AB対談」は無視できない連載だった。 これは、A氏とB氏によるビールトークで、タイトルはアサヒビールの頭文字をもじっている。ゲストの職業によって、テーマがさだまっている場合もあるが、その多くはビールを肴にした気ままなおしゃべり。 PR色をできるだけ排する編集方針のため、アサヒビールをほめるような発言は、意識的にはずされていた。
毎号数ページの誌面を割いた「AB対談」には、山本為三郎の財界での顔の広さ、飯沢の人選の巧みさがあいまって、多彩なA氏とB氏が登場した。 本稿の巻末にリストを載せたが、各界の著名人や一流の学者の名がならび、“品”と“格”、いずれも遜色はない。 謝礼は安く、ときにはビールの現物支給がおこなわれたらしいが、クレームはすくなかったという(鶴屋八幡がスポンサーの『あまカラ』のように、謝礼が現物支給の戦後のPR誌は、ほかにもあった)。
「AB対談」を読んでみると、じっくり読ませるには文字量がすくなく、ビール文化について論じるようなむずかしい内容ではない。 奇のてらわないおしゃべりに終始していて、軽い読み物になっている。それだけに読者の支持は高く、第34号(昭和28年6月号)の「愛読者アンケート結果発表」では、人気連載の第1位に輝いた。
もちろん、他愛のないビールのおしゃべりだけでは、魅力がない。そこで「AB対談」では、ホスト役のインタビュアーを用いず、連載対談のスタイルをとらなかった。 これにより顔ぶれはつねにかわり、組み合わせの妙がたのしめる。
たとえば、第52号(昭和29年12月号)では、平野威馬雄と三遊亭金馬の顔合わせがユニーク(*5)。 どういう人選意図かと思いきや、ウマ年最後の掲載号なので、名前に“馬”がつくふたりを呼んできた……だけのこと。しかも、お互いに親交があるわけでもなく、 仏文学者の平野がインタビュアーとなり、金馬(3代目)がまじめに受け答えする様子がおかしい。

*5 「AB対談」平野威馬雄と三遊亭金馬(『ほろにが通信』第52号)
第13号(昭和26年9月号)では、岡本太郎と杉村春子の組み合わせが実現した(*6)。 強烈なオーラを放つ両者のトークは、岡本の飲みっぷりを見た杉村が《あら、岡本さんのお飲みになる形、いいわね》と賞賛するところから始まり、 岡本がパリで目撃したビールを飲む少年の話、花柳章太郎の酒酔い演技、女優としての色気へと話が膨らんでいく。 それでいて、互いの分野に踏み込んで論じあうほどの専門性はなく、ビールを飲みながらの世間話に終始している。それが逆にいい。

*6 「AB対談」岡本太郎と杉村春子(『ほろにが通信』第13号)
もうひとつの魅力として、わずかな行数のなかにゲストの語り口を再現し、その人柄をそのまま伝えた構成のうまさがある。 速記と構成は、すでに30年のキャリアを持っていた秋山節義(*7)が担当した。秋山は、国会の速記者から朝日新聞社へ転じた人物で、 『週刊朝日』の徳川夢声対談「問答有用」などを手がけた、対談の構成をおこなうことも多く、秋山が「AB対談」を担当したのは当然、飯沢匡の推薦によるものだろう。

*7 秋山節義(『ほろにが通信』第55号)
秋山の速記のたしかさ、構成のうまさは、第34号(昭和28年6月号)の「AB対談」によくあらわれている。ゲストは、安藤鶴夫と桂文楽(*8)。 この粋人ふたりが、浅草界隈のうなぎ、そば、どじょうの名店をめぐりながらハシゴ酒をたのしみ、同時進行でトークがすすむ。そのなかに、安藤のこんな発言があった。

*8 「AB対談」安藤鶴夫と桂文楽(『安藤鶴夫・四谷に住んだ直木賞作家』新宿歴史博物館/平成11年7月
《死んだ小さんがね、上野の鈴本の、前ッ側のたべもの横町ね、あそこのトンカツ屋へとびこんでね、立ったままビールを1本きゅうと引かけて、塩をね、ちょッいとこうつまんでね、そいで帰ってった。 よかったね、あれは。鮮やかなもんだったね、あののみッぷりは》
実際には、ここまで流暢にしゃべることはむずかしい。それを、その場を想起させるように活字化したところに、秋山の速記と構成のうまさがある。 事実、鬼の編集長として知られた扇谷正造が、《速記の天才だった。正確無比、仕上げが完ぺき》(『辰野隆随想全集5』月報)と書いたほどである。 飯沢にしろ、秋山にしろ、『ほろにが通信』はよきスタッフにめぐまれた雑誌だった。
*
企業PR誌には、クライアントが自己規制しすぎたあまり、企画や記事に過剰なチェックを入れる悪しき習慣がある(とくに編集を外部に発注しているばあい)。 でも、『ほろにが通信』には、そうした心配がない。エッセイにしろ、「AB対談」にしろ、読者を飽きさせない工夫が施されていたし、 飯沢匡や業務第一課長の長谷川遠四郎の了解さえあれば、あとは自由に編集することができた。「AB対談」がもし、別セクションのゴリ押し、 山本為三郎をホスト役とする連載対談になっていたら、どうだろうか。先述したようなバラエティーの豊かさは生まれなかったはずだ。
いまでも多くの企業PR誌が出されているが、著名人ほど相応のギャラを要求してくるし、間違ってもビールのつめあわせでは済まされない。 『ほろにが通信』は、企業、代理店、所属事務所、所属団体がのんびりしていた時代の産物、といえるかもしれない。
(つづく)
- 巻末資料:「AB対談」リスト
-
■No.1(昭和25年10月号)
「酔っても楽しく」
渡辺紳一郎(話の泉同人)×山本為三郎(朝日麦酒社長)
■No.2(昭和25年11月号)
「苦心の要る宴会」
佐藤尚武(参議院議長)×高橋龍太郎(日本商工会議所会頭)
■No.3(昭和25年12月号)
「音楽家はビール好き」
堀内敬三(音楽評論家)×山本為三郎
■No.6(昭和26年3月号)
「ビールと女性」
阿部艶子(作家)×藤川栄子(洋画家)
■No.7(昭和26年4月号)
「ピルゼン風とは」
有馬大五郎(音楽家)×遠藤慎吾(演劇評論家)
■No.8(昭和26年5月号)
「倹しく楽しく飲もう」
山本嘉次郎(映画監督)×古川緑波(俳優)
■No.9(昭和26年6月号)
「AB対談」
林芙美子(作家)×渋沢秀雄(随筆家)
■No.12(昭和26年8月号)
「夕べをビールと共に」
浜本浩(作家)×長谷川春子(洋画家)
■No.13(昭和26年9月号)
「初秋!ビールの味いやまさる」
杉村春子(新劇俳優)×岡本太郎(洋画家)
■No.14(昭和26年10月号)
「病人も飲むビール」
高橋龍太郎(通産大臣)×武者小路公共(元駐独大使)
■No.15(昭和26年11月号)
「飲んで癒った病気」
奥野信太郎(慶大教授)×喜多実(能楽家)
■No.16(昭和26年12月号)
「かくて宿酔はなし」
高橋忠雄(東大医学部助教授)×伊藤昇(朝日新聞論説委員)
■No.17(昭和27年1月号)
「人生の辛さをビールで甘く」
相良守峰(東大教授文学博士)×三雲祥之助(洋画家)
■No.18(昭和27年2月号)
「御婦人にも向くビールを」
城戸四郎(松竹副社長)×千田是也(演出家・俳優)
■No.19(昭和27年3月号)
「欲しい女だけの酒場」
深尾須磨子(詩人)×佐藤美子(声楽家)
■No.20(昭和27年4月号)
「お魚も飲めば酔う」
末広恭雄(東大教授・水産学)×松田トシ(声楽家)
■No.21(昭和27年5月号)
「美味しかった最初のビール」
尾高朝雄(東大教授法学博士)×長岡輝子(新劇演出家)
■No.22(昭和27年6月号)
「ビールは酒にあらず」
三神修(経済学博士)×小川太一郎(工学博士)
■No.23(昭和27年7月号)
「仕事の後のビール一杯」
木村伊兵衛(写真家)×名取洋之助(写真家)
■No.24(昭和27年8月号)
「アサヒビールの創立を語る」
高橋龍太郎×山本為三郎
■No.25(昭和27年9月号)
「ビールを無駄にするな」
辰野隆(仏文学者)×石川欣一(評論家)
■No.26(昭和27年10月号)
「動物はビール好き」
丘英通(理学博士)×林寿郎(上野動物園企画係長)
■No.27(昭和27年11月号)
「のてには分らないこの気分」
桶谷繁雄(工学博士)×佐野周二(映画俳優)
■No.28(昭和27年12月号)
「懐しのエリセーフの店」
米川正夫(ロシヤ文学者)×東山千栄子(新劇俳優)
■No.29(昭和28年1月号)
「ハイカラで野暮な、のてツ子気質というもの」
中島健蔵(評論家)×三木鶏郎(作曲家)
■No.30(昭和28年2月号)
「教科書にあった太陽脾卑酒」
魚返善雄(中国文学者)×高木健夫(読売新聞論説委員)
■No.31(昭和28年3月号)
「恋愛は仕事のアクセサリー」
市川紅梅(新派俳優)×藤間紫(舞踊家)
■No.32(昭和28年4月号)
「朧月夜麦酒泡談」
尾上梅幸(歌舞伎俳優)×戸板康二(劇評家)
■No.33(昭和28年5月号)
「古風な、あまりに古風な」
荒垣秀雄(朝日新聞論説委員)×福岡誠一(『リーダーズダイジェスト日本語版』編集長)
■No.34(昭和28年6月号)
「生きているのれん魂」
安藤鶴夫(劇評家)×桂文楽(落語家)
■No.35(昭和28年7月号)
「東京のパリ祭」
ロベール・ギラン(『ル・モンド』特派員)×高橋那太郎(NHK文芸部員)
■No.36(昭和28年8月号)
「スポーツの後の一杯こそ」
富永正信(朝日新聞運動部長)×大島鎌吉(毎日新聞運動部副部長)
■No.37(昭和28年9月号)
「女性は酒のみに寛大か」
大宅壮一(評論家)×扇谷正造(『週刊朝日』編集長)
■No.38(昭和28年10月号)
「勝っても負けても」
島田孝一(早稲田大学総長)×潮田江次(慶応義塾塾長)
■No.39(昭和28年11月号)
「ジャズの中に真の音楽を」
服部正(作曲家・指揮者)×小島正雄(楽団ブルーコーツ主宰者)
■No.40(昭和28年12月号)
「学者もビールがお好き」
藤岡由夫(東京教育大理学部長)×都留重人(一橋大経済研究所長)
■No.41(昭和29年1月号)
「ビールは細く長く」
河井弥八(参議院議長)×山本為三郎
■No.42(昭和29年2月号)
「鰻談・うまい、釣のあとのビール」
宮川曼魚(随筆家)×檜山義夫(東大教授)
■No.43(昭和29年3月号)
「ホロッと酔って、ホロッと消える」
神近市子(参議院議員)×阿里道子(ラジオスター)
■No.44(昭和29年4月号)
「開幕劇で野心的な試みを」
内村直也(劇作家)×尾上九朗右衛門(歌舞伎俳優)
■No.45(昭和29年5月号)
「面白い動物の酔態」
岡田要(科学博物館館長)×内山賢次(英文学者)
■No.46(昭和29年6月号)
「随時随所麦酒快」
高村豊周(鋳金家)×前田雀郎(川柳家)
■No.47(昭和29年7月号)
「同行二人 ビールぞめき」
加藤芳郎(漫画家)×岡部冬彦(漫画家)
■No.48(昭和29年8月号)
「われらは”明治の末席”輩」
池島信平(文藝春秋新社編集局長)×中屋健弐(東大文学部助教授)
■No.49(昭和29年9月号)
「山と料理とビール」
辻二郎(工学博士)×黒田初子(随筆家)
■No.50(昭和29年10月号)
「お茶のビール・胃酸のシャンパン」
飯沢匡(劇作家)×丹阿弥谷津子(新劇女優)
■No.51(昭和29年11月号)
「ビールに明け、ビールに暮れる」
清瀬保二(作曲家)×石井歓(作曲家)
■No.52(昭和29年12月号)
「ウマ年よさようなら」
平野威馬雄(仏文学者)×三遊亭金馬(落語家)
■No.53(昭和30年1月号)
「新春AB対談」
久保田万太郎(作家・演出家)×吾妻徳穂(舞踊家)
■No.55(昭和30年6月号)
「酒・その理論と実際」
渡辺八郎(東京国税局鑑定官室長)×長谷川幸保(日本バーテンダー協会会長)
【備考】No.4、5、10、11、54休載。番外編の座談会としてNo.2「珍味・ビールと料理」(矢野目源一×福田恆存×長岡輝子)、No.11「酔うことが紳士の嗜み」(西脇順三郎×辻直四郎×福原麟太郎)、No.24「ええとこや大阪は」(飯島幡司×坂口祐三郎×湯木貞一×徳光こう×食満南北×須磨対水×山本為三郎)、No.54「京都ほろにが座談会」(湯川秀樹×竹内逸×伊吹武彦×岩井武俊)がある。
- プロフィール
- 濱田研吾(はまだ・けんご)
- ライター。昭和49年、大阪府交野市生まれ。
- 日本の放送史・俳優史・広告文化史をおもに探求。
- 著書に
- 『徳川夢声と出会った』(晶文社)、
- 『脇役本・ふるほんに読むバイプレーヤーたち(書籍詳細へ)』(右文書院)。
- 『三國一朗の世界・あるマルチ放送タレントの昭和史』(清流出版)。
- 注記
- 本稿の無断転載は、ご遠慮ください。
- 図版は、特記なきものは筆者所蔵のものです。