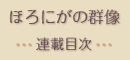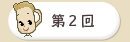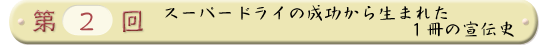● 濱田研吾 ●

*1 山本為三郎(『山本為三郎翁傳』朝日麦酒/昭和45年4月)
「商品をして、すべてを語らしめよ」。資生堂の初代社長、福原信三が遺した言葉だ。 「品質で、商品のすべてを表現しなければならない」という意味で、資生堂の企業哲学としていまも受け継がれている。
その言葉を、金科玉条とした人物がいる。多くの女性イラストレーションで広告をいろどり、資生堂の企業イメージを高めた山名文夫である。 しかし、山名は、自分のイラストレーションや広告制作物が“作品”として評価されることに不満をおぼえた。 社史や企業博物館にポスターや広告が並べられることも嫌がった。 ようするに商品が第一であって、広告がひとり歩きしてもなんの意味もなさない、という想いのあらわれである。
その意味からいくと、朝日麦酒の宣伝活動は、やや、広告がひとり歩きしたともいえた。 朝日麦酒の宣伝活動をひもとく前に、まずは、この点について書いてみたい。
*
朝日麦酒の前身は大阪麦酒(明治22年創業)で、明治36年に大阪麦酒・日本麦酒・札幌麦酒の3社が合併して大日本麦酒が誕生する。 その大日本麦酒が、昭和24年、GHQの「過度経済力集中排除法」により、朝日麦酒(現・アサヒビール)と日本麦酒(現・サッポロビール)の2社に分割・独立される。 こうして国産のビール業界は、アサヒ・ニッポン・キリンの3大ブランドがシェア争いをしていく。朝日麦酒の宣伝活動も、ここからはじまった。
昭和26年当時のシェアは、朝日35.3%、日本35.4%、麒麟29.3%という割合だった。しかし、アサヒブランドの東京での知名度は低く、朝日のシェアは年々下がっていく。 市場ニーズへの対応の遅れ、全国規模でブランド展開する麒麟の独走など、シェアを下げた要因も少なくない。昭和30年代には、サントリーがビール市場に参入。 麒麟に対抗するために打ち出された朝日・日本の再合併案も実現せず、さらなる苦戦を強いられた。
つまり、飯沢匡をはじめ、鬼才のクリエーターたちが揃ったわりには、朝日麦酒の宣伝活動は売り上げに結びつかなかった。 結びつかないどころか、むしろ下がった。創業直後からの宣伝活動や広告制作物は、『ほろにが通信』をはじめ、新しかったし、ユニークだった。 でも、福原信三や山名文夫の視点で考えれば、そこにどれほどの意味があるのか……ともいえる。
当時のクリエーターによるさまざまなアイデアに対して、朝日麦酒社長の山本為三郎(*1)は、協力を惜しまなかった。 ただ、そこは財界の大物であり、目のこえた経済人である。漫画家の近藤日出造からインタビューを受けたさい、山本は、朝日麦酒の宣伝活動について苦言を呈している。
《『ほろにが通信』というのがございましょ、あれを人にきくと、面白いなというんだけれど、どこのビール会社がやっとるのか知らんのですよ。 今日も実は宣伝部を怒りつけたんですが、この頃マンネリズムになりすぎているんです。 君らの個性が勝ちすぎているんじゃないか、読む人、見る人を度外視して君の広告をしとるんじゃないか、といったんだが、宣伝広告のようなものの場合、個性を他人に押しつけるのはよくないんです。》 (「僕の診断書16」『中央公論』昭和30年7月号)
この席で近藤は、「お宅は宣伝がうまいですな」と言って、山本を少し怒らせている。近藤が得意とした皮肉とも思えるが、業界の見方もそれに近いところがあったのだろう。 売り上げは良くないけれど、広告はおもしろい。そういった評価だったのかもしれない。
ただ、広告のおもしろさに、山本は同調しなかった。昭和30年代なかばになると、創業直後から朝日麦酒の普及につとめた宣伝関係者たちも、少しずつそこから離れていく。 そして、昭和41年に山本が急逝し、飯沢匡たちが築いてきた宣伝文化はいちおうの終止符を打つ。
創業から山本が亡くなるまでの17年間で、朝日のシェアは10%以上も下落した。その後も、生ビール戦争に敗れるなど、朝日は凋落の一途をたどる。 昭和60年には、シェア10%の大台を割り、なんとも“ほろにがい”状況におちいってしまった。
ここで救世主となるのが、住友銀行から送り込まれた樋口廣太郎である。 樋口は、コクとキレの辛口ビール「スーパードライ」を世に問い、アサヒブランド復活のきっかけをつくる。 こうして朝日麦酒は、創業から38年たって初めてシェアが上向いた。

*2 高山房二編『アサヒビール宣伝外史 揺籃期の栄光と挫折』(中央アド新社/平成11年3月)
このスーパードライの成功ののち、朝日麦酒の宣伝史が1冊にまとめられている。平成11年発行の『アサヒビール宣伝外史 揺籃期の栄光と挫折』(*2)である。 歴代の宣伝責任者による座談会を中心に編まれ、朝日麦酒と関係の深い広告代理店「中央アド新社」が出した。 実名を挙げた他社(他者)への批判もあり、市販されていないが、創業直後の宣伝事情が語られた貴重な文献である。 本書には、アサヒビール取締役会長(当時)の瀬戸雄三が、こんな序文を寄せている。
《今日、幸いわが社は脚光を浴び、首位奪還に至るその歴史が多くの社外の人々の手で、好意をもって書き記されている。 しかし歴史には、その渦中に在った者でなければどうしてもわからない内実がある。》
瀬戸の言葉のとおり、樋口廣太郎の陣頭指揮による復活劇については、多くの本が出版されている。 しかし、それ以前の記録は、山本が憂いた「個性が勝ちすぎている」宣伝活動とともに、あまり書き記されていない。
当事者はおそらく、創業まもない朝日麦酒の宣伝活動について、それなりの自負を抱いていたと思う。ただ、悪化するばかりの業績を前に、お世辞にも「広告はおもしろかった」とは言えなかった。 それがスーパードライの成功でシェアが好転し、創業当時の宣伝活動を知るOBたちが集い、後進への糧とするべく本にまとめた。 そのことは、「揺籃期(物事が発展する初期の段階)の栄光と挫折」という言葉からもうかがえる。
もちろん、この1冊だけでは不備もある。ライバルの日本麦酒が、ほろにが君をまねたようなキャラクター「ビールの王さま」でキャンペーンを広げたことなど、紹介されていないエピソードも多い。 当事者による座談会なので、話題が社内にとどまり、全方位的に広がっていかないのも納得できる。
これからテーマにしていきたいのは、“作品”としての宣伝活動であって、朝日麦酒のシェア凋落、それにつづく復活劇ではない。
山名文夫の女性イラストレーションは、資生堂の企業哲学とは関係なく“作品”としても美しかった。それと同じように、創業まもない朝日麦酒の宣伝文化は、ユニークであり、“作品”として魅力的だったと思う。 「広告をして、すべてを語らしめよ」という言葉があってもいいのでは、と感じるのだが。
(つづく)